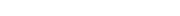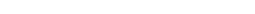【デコボコの歯を矯正しないとどうなる?】矯正治療のメリットデメリットを解説
東京都渋谷区広尾にある歯医者『モウリデンタルクリニック』院長の毛利です。
今回のテーマは「デコボコの歯のリスクや矯正治療のメリットデメリット」について解説していきます。
矯正治療をする前にどんなことが必要なのか?矯正治療のメリットやデメリット、リスクを知っておくことはとても大事です。『思っていたのと違った』となる前に、リスクなどを把握してから矯正治療の相談してみてください。
目次
1.矯正治療のメリット
①歯周病の有無
歯並びを整えることで、歯と歯の余計な重なりが無くなります。これによって食物や唾液の流れがよくなり、歯や歯肉に食物が停滞し難くなります。また、整った歯列と調和した歯肉は歯磨きやうがいの効果を上げるので、歯磨きの効率が向上します。
歯磨きをいくら頑張っても、磨き残しが長期に渡れば、そこから虫歯や歯周病に至るので、
悪い歯並びは様々なリスクの原因になります。
また、歯周病の原因は歯周病菌だけでなく、歯にかかる不適切な力があります。
歯並びやかみ合わせが悪いままだと、歯に余計な力がかかりすぎてしまい、その歯を支えている周囲の骨が吸収(破壊)されてしまい、一般的な歯周治療だけでは対応できない場合があります。こういう場合は、矯正で歯を適切な場所に移動させることで、歯に余計な負担がかからなくなり、歯周病予防につながります。また、すでに骨の吸収(破壊)を伴ってしまった歯についても、歯が移動することにより周囲の骨代謝が活性化し、再び骨が再建されるケースもあります。つまり、歯周病対策として矯正治療は有効だということです。
②口元と横顔がキレイになる
綺麗な歯並びは、口元と横顔がキレイになります。
矯正治療は口元の美しさももちろんきちんと考えておるので、顔貌が大きく改善することがあります。
ただし症例によっては、大きく改善しない場合もあります。あくまでも機能性を重視し、
その結果に基づいて綺麗になることが大切です。機能を疎かにして美しさを追求してはなりません。たとえ一時的に綺麗になったとしても安定せず、様々な問題を生むことになります。
③咀嚼効率の向上
上下左右の歯の形状、歯の位置関係にはきちんと意味があり、これら正しく関係していることで、食物を適切に効率よく粉砕し、唾液を効果的に利用できます。これにより消化器官へ
健康に維持し、歯を生涯にわたって用いることにつながります。
④歯を抜かない可能性が高くなる
成長期に適切なタイミングで矯正治療を行うことで、顎の成長を促し、将来歯を抜かずに
歯列を整えることが可能になります。(症例によってはそれでも抜く場合がある)
また、治療の早期介入で、矯正装置を最小限で簡易的なもので行える場合も少なくありません。 特に子供は早めの検診と、定期的な歯並びの観察を心がけるようにしてください。
⑤発音が良くなる
歯並びは、発音にも強く関連しています。例えば、歯と歯の間に大きな隙間がある場合は、歯列のすき間から息漏れが生じて、特定の言葉を正しく発音できないことがあります。
また受け口や上顎の歯が突出している場合に関しても、きちんと発音できないことがあります。歯列やかみ合わせの改善は、このような発音障害にも良い影響を与えます。
⑥本格矯正治療(大人の矯正治療)で手術を併用する可能性が低くなる
子供の時にきちんと歯並びの診査をすれば、ある程度は未来の予測ができます。
もちろん、全ての予測があたるとは限りませんが、定期健診を行うことで、
必要な治療を必要なタイミングで行うことができるようになります。
顎の成長が止まってからの矯正治療には限界があり、重度の骨格性の問題を帯びている場合は上下額の骨を外科的に切除する場合があります。
これを避けるためには、早い段階で未来の歯並びを予測し、できるだけ成長期の中で
理想的な咬合に誘導することです。
⑦正面から見た顎の曲がりの程度を減らす
顔貌はどうしても遺伝的要素が強く、日常の習慣では変えられないものです。
しかし顎の成長をコントロールしたり、噛み合わせを適切に導くことで
見た目の顎の曲がりを最小限にし、遺伝的要素による影響を小さくすることになります。
成長期における矯正診断を早期に行うことが大切です。
⑧コンプレックスの早期解消
口元は顔貌に大きく影響します。また、成長と共に顔貌が大きく変化する場合もあるので、
成長期の段階で矯正診断を行い、必要に応じて矯正治療を行うことは、乱れた歯並びによって自然に笑えない、大きく口を開けることができないなどの、口元に対するコンプレックスを早く解消することにつながります。
2.矯正治療のデメリット(リスク)
①違和感について
一般的には、口の中に矯正装置をつけることで、日常生活において違和感を完全排除することはできません。装置を広範囲にわたって装着した日から数週間は強い違和感を覚えるでしょう。もちろん多くの方は慣れるものですが、なかなか慣れずに苦労する方もいます。
②口内炎について
矯正装置が頬や唇の内側に当たって口内炎になることがあります。
特に装着してすぐの場合は、口内炎になりやすいので、注意が必要です。
唾液の分泌量が少ないと、口内炎になり易かったりするので
唾液の分泌を促すことが大切です。ほとんどの場合、時間の経過とともに、
自然に改善してくるケースが多いのですが、なかなか治らない場合は、
矯正装置への加工や変更が必要となります。
③痛みについて
歯に矯正力をかけると、装置の種類とかける力にもよりますが、一番最初の1週間~2週間は歯に痛みが生じます。特に最初の一週間は食事が困難になる場合もあるため、いきなり強い力をかけるのではなく、最初は弱めの力でスタートして、徐々に強い力をかけていくことで、矯正中の痛みを最小限に抑えることができます。マウスピース矯正の場合は、矯正力がワイヤー矯正に比べて弱いので、矯正力による痛みは少ない傾向にあります。
矯正治療中の歯の痛みはある程度覚悟しなければなりませんが、痛みについては
感じ方も人それぞれですから、痛みが出現する時期、
痛みを最小限にするための治療法について担当医とよく相談してください。
④歯磨きについて
矯正装置によって、食物が歯と歯の間、歯と装置の間に詰まりやすく、通常の歯磨きでは
なかなか取れません。ゆえに歯ブラシだけでなく、口腔内洗浄機やタフト歯ブラシなどを用いてこまめに食物の残渣を取り除くようにしましょう。また、定期的に歯科医院でクリーニングすることも有効です。虫歯になり易いので、矯正治療中は間食を控え、特に甘いものや甘い飲みものを避けるようにしましょう。
⑤歯根吸収について
矯正治療においては、ある一定の割合で歯根吸収を認める報告があります。
その原因については様々ですが、歯に強い力をかけることで生じる可能性が高くなります。
また歯を動かす方向、動かし方によっても歯根吸収を生じる確率が変わります。
上下顎切歯が特に起こりやすいので、注意が必要です。
歯根吸収した歯の予後については様々な報告がありますが、結論として、
歯の生存率にはほとんど影響しないとのことです。
ただし、できるだけ歯根吸収を避けるためにも、強い矯正力をかける場合は、
注意が必要です。
⑥歯の神経の失活について
これも強すぎる矯正力で生じることが稀にありますが、噛み合わせの状態によっても起こることがあるので、特に気を付けなければなりません。歯の神経が失活してしまうと、
将来、歯の生存率が著しく低下するため、絶対に避けなければなりません。
強すぎる矯正力は、リスクが高いので、できるだけ弱い矯正力で歯を移動させることが理想です。
⑦歯肉退縮について
矯正治療中、治療後に歯肉が下がり歯の根が一部露出することがあります。歯を支えている骨が薄い場合や、元々重なり合っていた歯が移動することで、歯と歯の間に隙間が生じ、歯肉が下がったように見えたり、歯の移動に伴い歯肉が下がることがあります。
小児矯正の場合は成長を伴うためあまり歯肉退縮は起こりませんが、成長が完了した大人の矯正治療をされる方は歯の移動量が多いほど、この歯肉退縮を生じる可能性が高くなります。
また、歯肉退縮により歯の間に生じる隙間(ブラックトライアングル)は、矯正治療をしなくてもエイジング(加齢)によっても起こります。
矯正治療を始める前に、歯肉退縮量はある程度予測が立てられるので、治療開始前に
担当医に確認するようにしてください。
⑧親知らずについて
親知らずを残したまま矯正治療を行うと、ケースによっては十分に治療を施せないこともあります。また、過剰歯や埋伏歯もこれと同様であり、矯正治療前に、そのような歯が無いかどうか確認し、必要に応じて抜歯するようにしてください。
⑨顎関節症について
噛み合わせと顎関節症には因果関係がないという意見がありますが、
これは大きな間違いです。因果関係がある場合と無い場合があり、
正しく見極める必要があるということです。また顎関節症があるからと言って
直ちに噛み合わせを改善するということではありません。
歯並びやかみ合わせにはきちんと意味があり、各個人の正解があります。
明らかに顎関節に対して悪い影響を与えている噛み合わせや歯並びであるならば、噛み合わせの調整や矯正治療で改善することが必要となります。ただし、まずは可逆的な方法で改善の期待値を確認することが重要です。
そして、矯正治療中に顎関節症が発症する場合もあります。かみ合わせが一時的に変化することで顎関節に負担がかかり、開口時、閉口時の顎関節の痛みを伴うことがあります。
この場合は、ほとんどが一時的なものなので心配はありませんが、必要に応じて矯正法を変更する場合があります。また、食いしばりや噛みしめは顎関節症を誘発することもあるので、
安静時は歯と歯を接触させないようにしましょう。
⑩後戻りについて
矯正治療後に、動かした歯を留めることは容易いことではありません。
むしろ、移動が完了してから数年間は歯が元の位置に戻ろうとする力が働くので、
移動完了後も定期的に検診を行う必要があります。
特に成人矯正の場合は、周囲組織の成長を伴わないので矯正後の歯並びが顎関節や筋組織と直ちに調和するとは限りません。歯の位置を変化させても、噛み合わせに影響するあらゆる力との調和がとれないとかみ合わせが悪い状態になることもあります。
矯正期間は、歯を移動させる期間だけを指すのではなく、移動完了後も歯をそこに留めておくための期間も含まれます。つまり、移動完了後も矯正治療は続いているということです。
移動完了後から少なくとも5年は経過観察を必ず行うようにしてください。
移動完了後に歯の後戻りがある場合、早急に対処することが大切です。
まとめ
いかがでしたか?
矯正治療を考える方は始める前にメリットとデメリットを把握したうえで治療の相談することが大切です。
モウリデンタルクリニックでは矯正のご相談も受け付けております。
当院での矯正治療をご検討される方は矯正治療についてのページをご覧ください。
矯正治療について
また当院のご予約はお電話・WEB予約で承っております。
ご予約はこちら
記事の著者:モウリデンタルクリニック 院長 毛利 啓銘
モウリデンタルクリニックは患者様の数十年後の健康を見据えた、総合的で一貫性のある歯科医療を提供するクリニックです。
特徴として、医学、科学に基づくだけでなく、患者本位に沿った総合的歯科医療を提案、実践します。これは予知性を持った、合理的かつリスクの低い歯科医療です。
患者様には、問題の原因、歯科医療の本質について分かりやすく説明し、各予防法、各治療法について適切に選択して頂く事を大切にしています。
経歴/所属学会
■東京歯科大学卒業
https://www.tdc.ac.jp/
■日本口腔インプラント学会所属
https://www.shika-implant.org/
■ドイツ Ankylos Implant認定医
https://www.dentsplysirona.com/ja-jp/explore/implantology/ankylos.html
■ドイツ XiVE Implant認定医
https://www.dentsplysirona.com/ja-jp/explore/implantology/xive.html
過去の記事
■歯の矯正をする前の注意点!必ず知っておいた方がいい矯正の知識